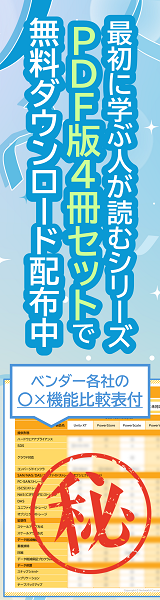
第7節はオブジェクトストレージ、ファイルストレージ、ブロックストレージの違い解説しました。 今回はストレージでよく使われる通信プロトコルと接続ケーブル・インターフェースについて解説します。


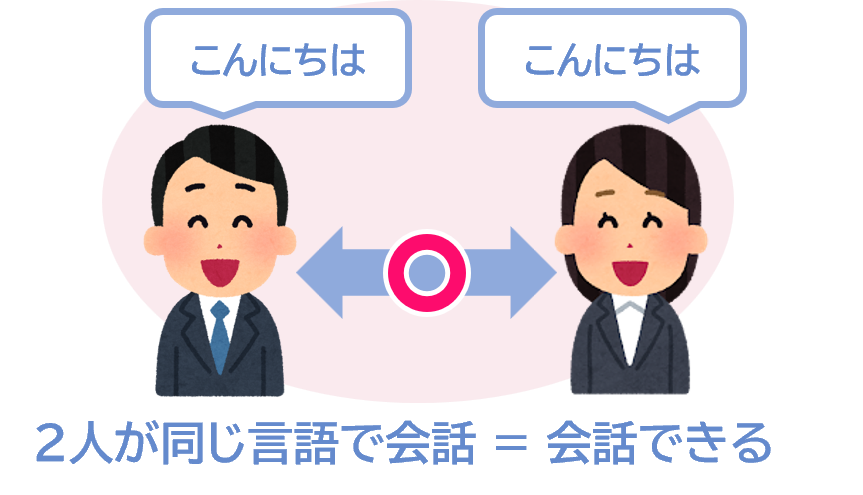
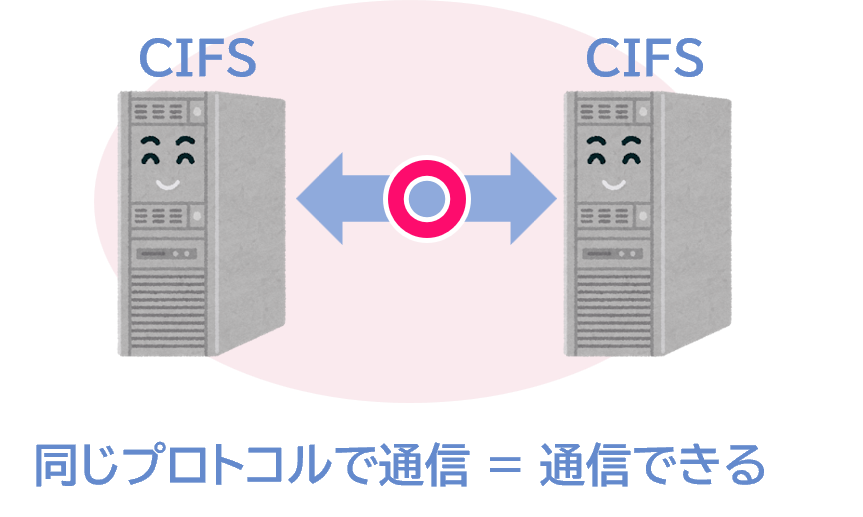
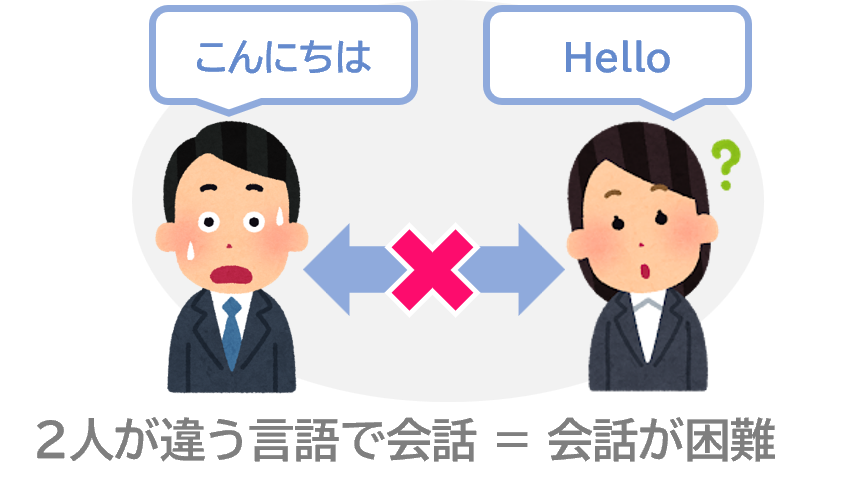
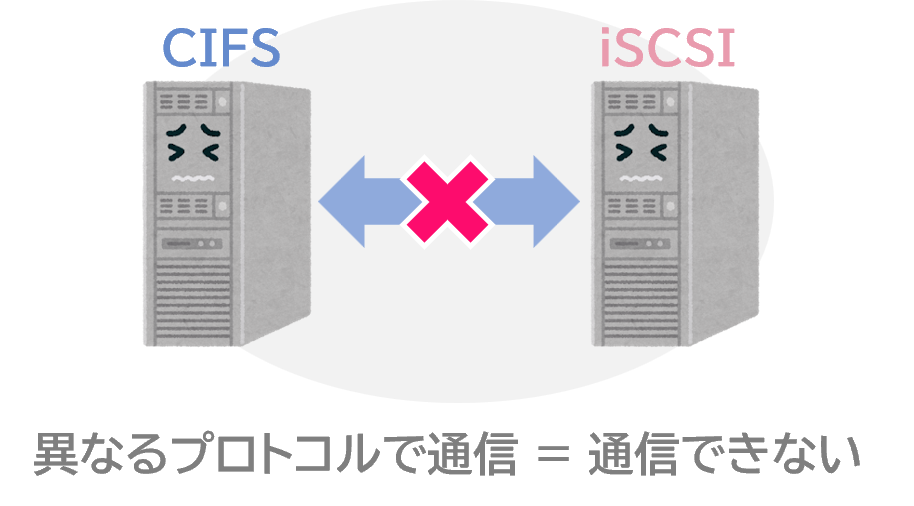


|
CIFS (SMB) Common Internet File System |
|
|---|---|
|
NFS Network File System |
|
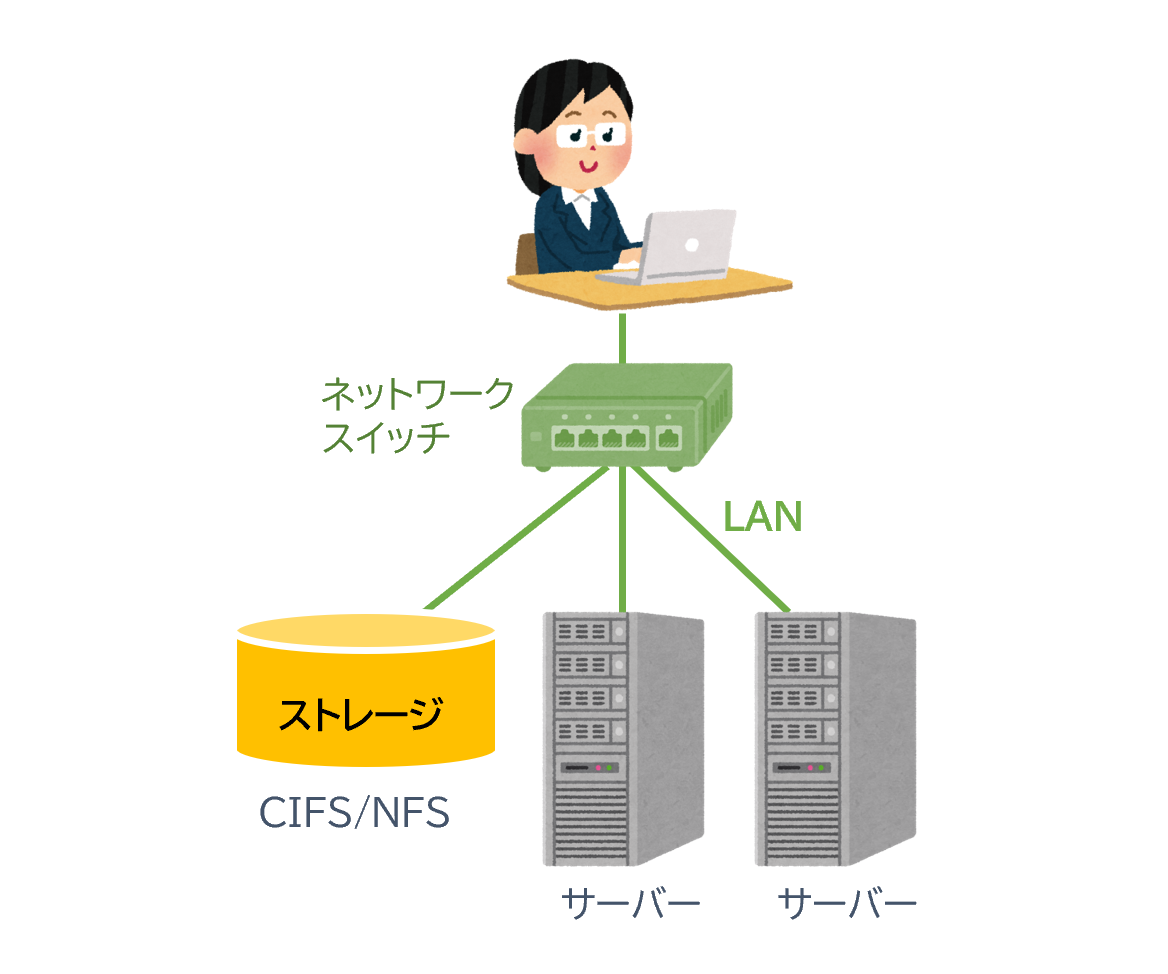
|
FC Fibre Channel |
|
|---|---|
|
iSCSI Internet Small Computer System Interface |
|
|
FCoE Fibre Channel over Ethernet |
|
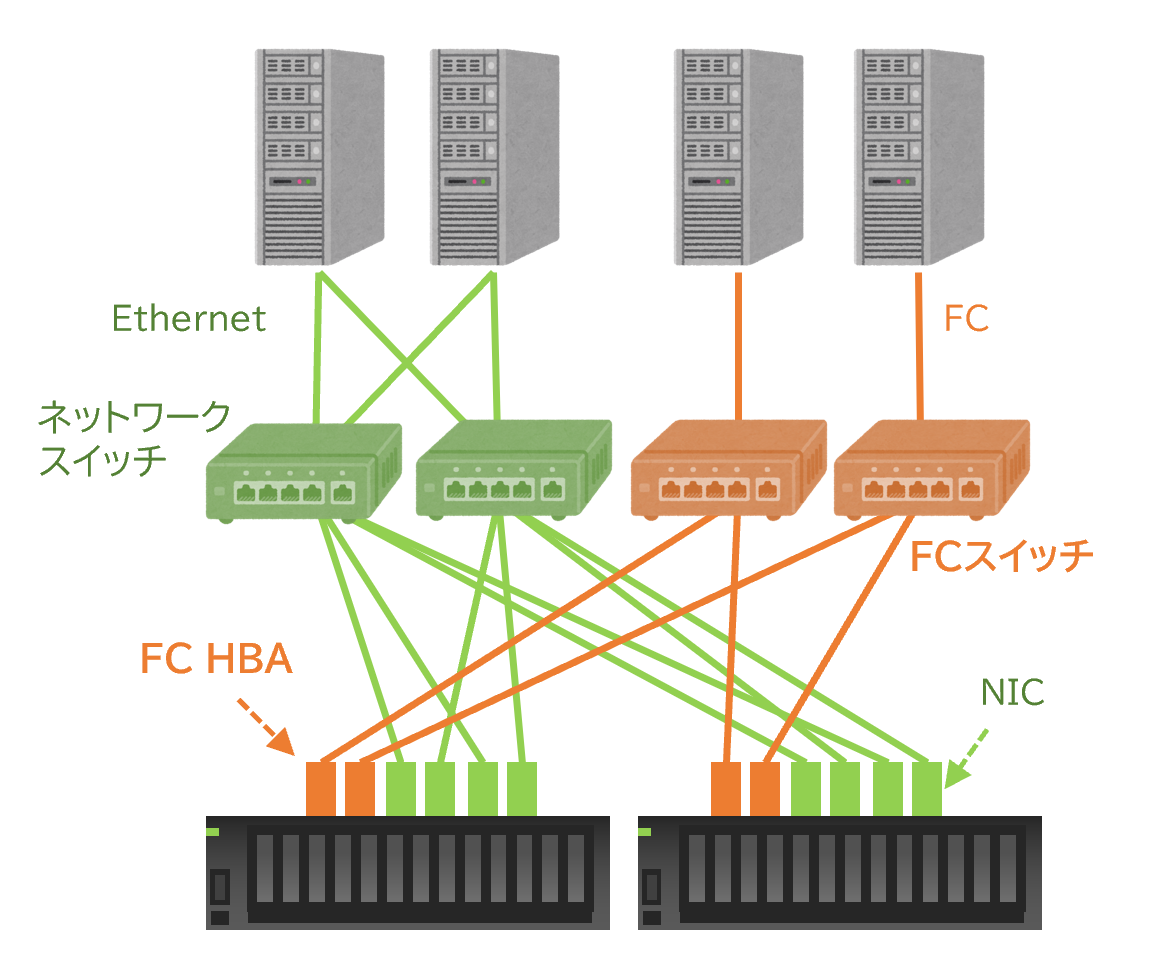
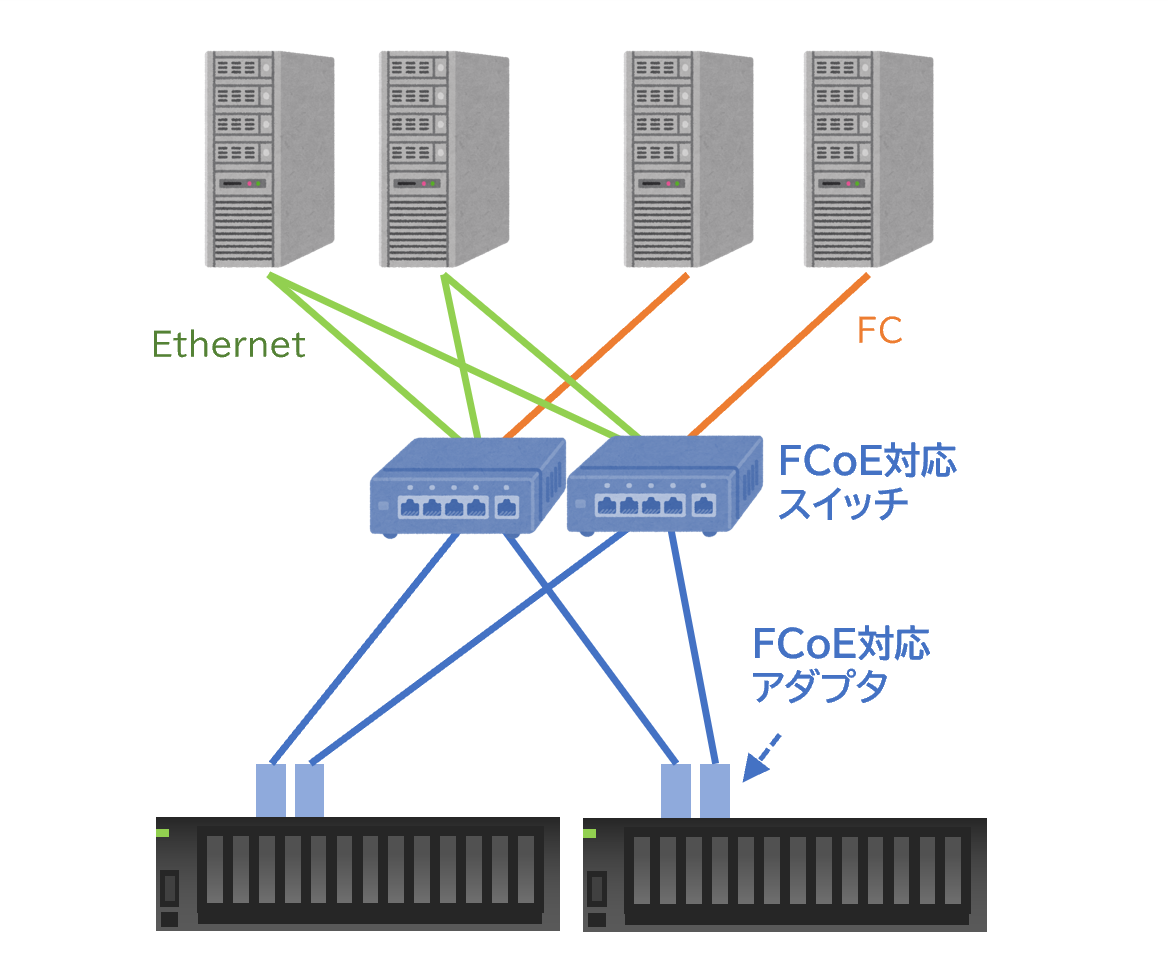




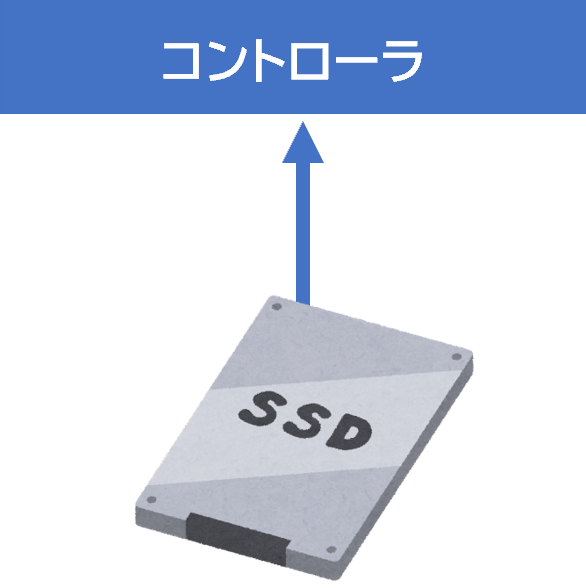
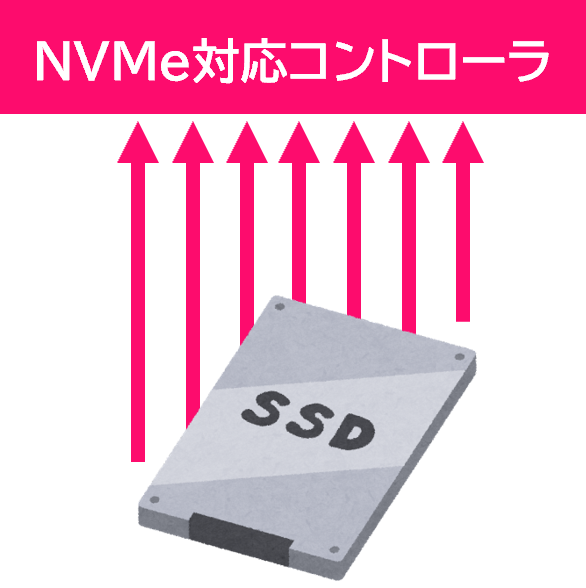

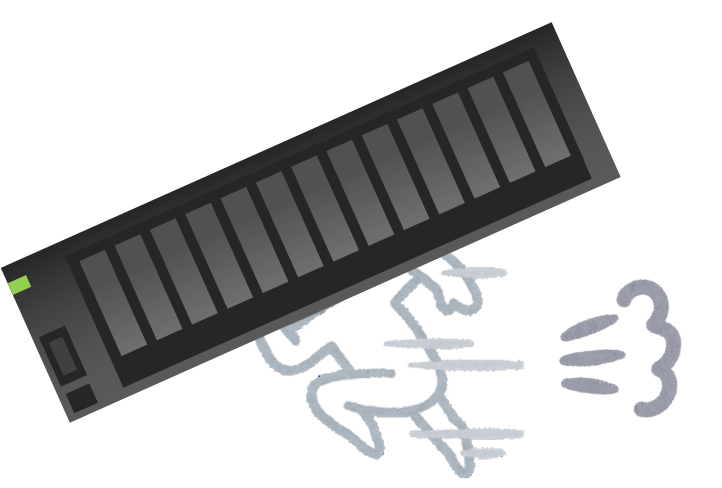




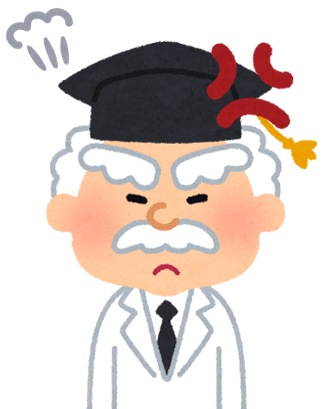
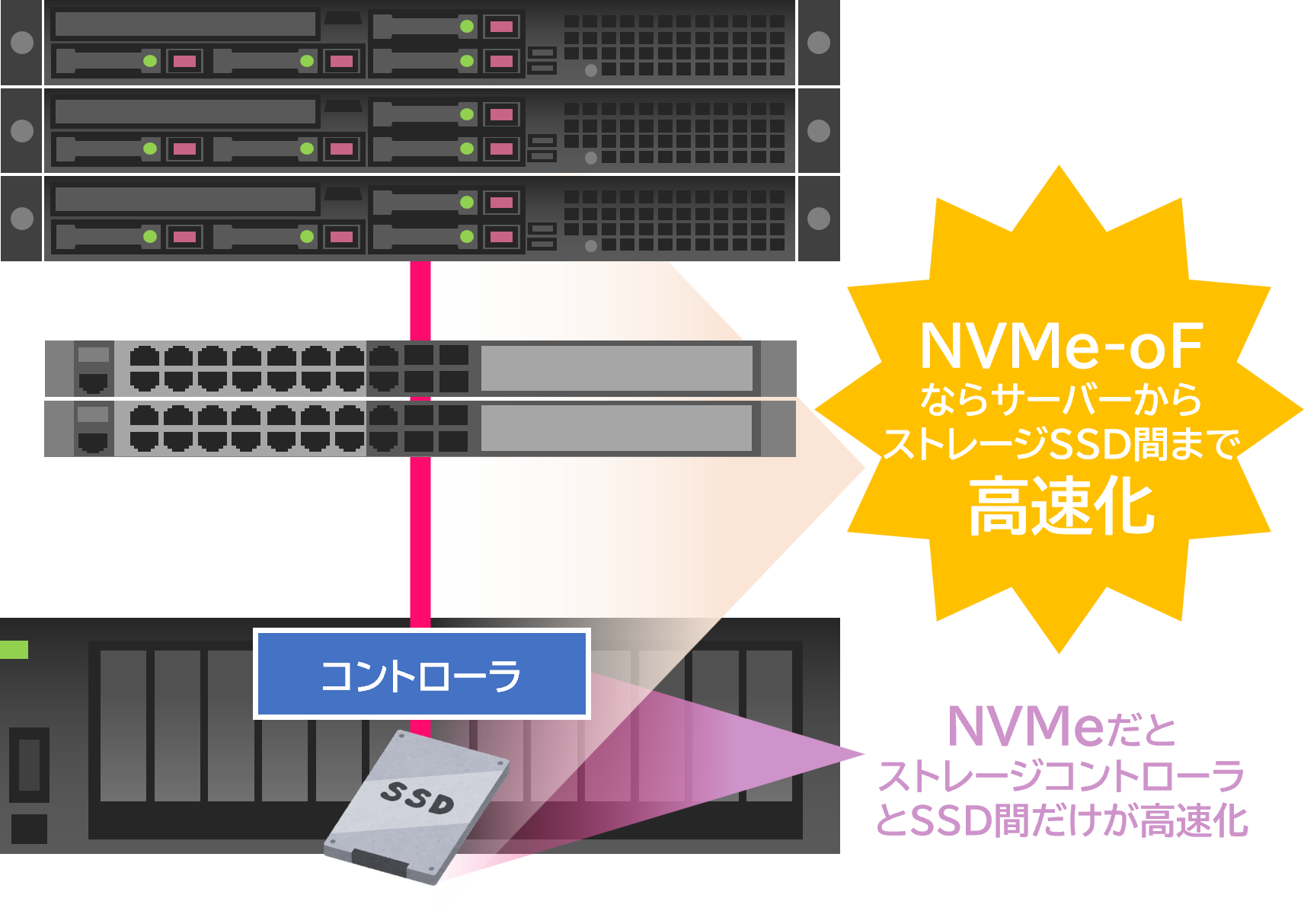







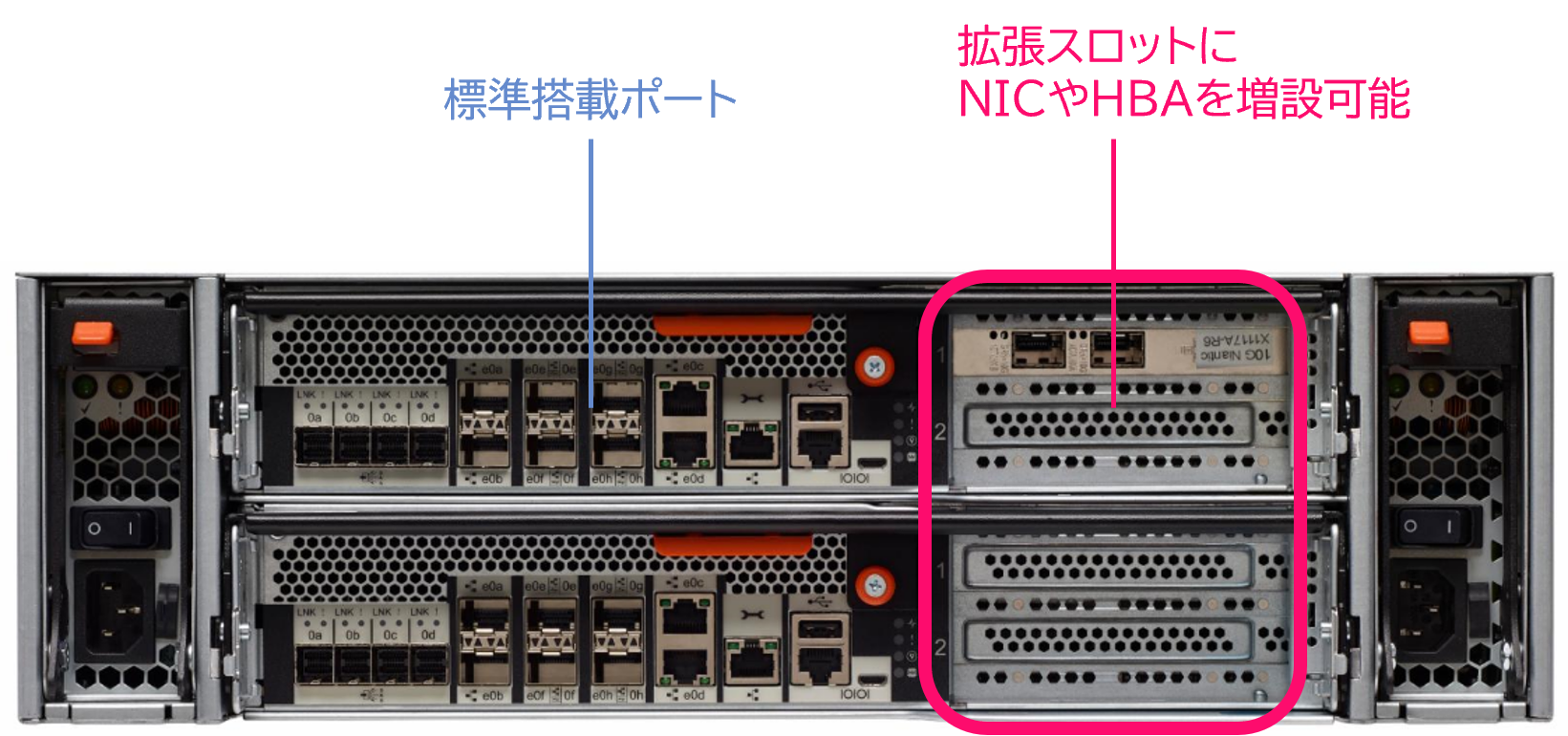

イーサネット接続(1000Base-T, 10GBase-Tなど)で利用される。
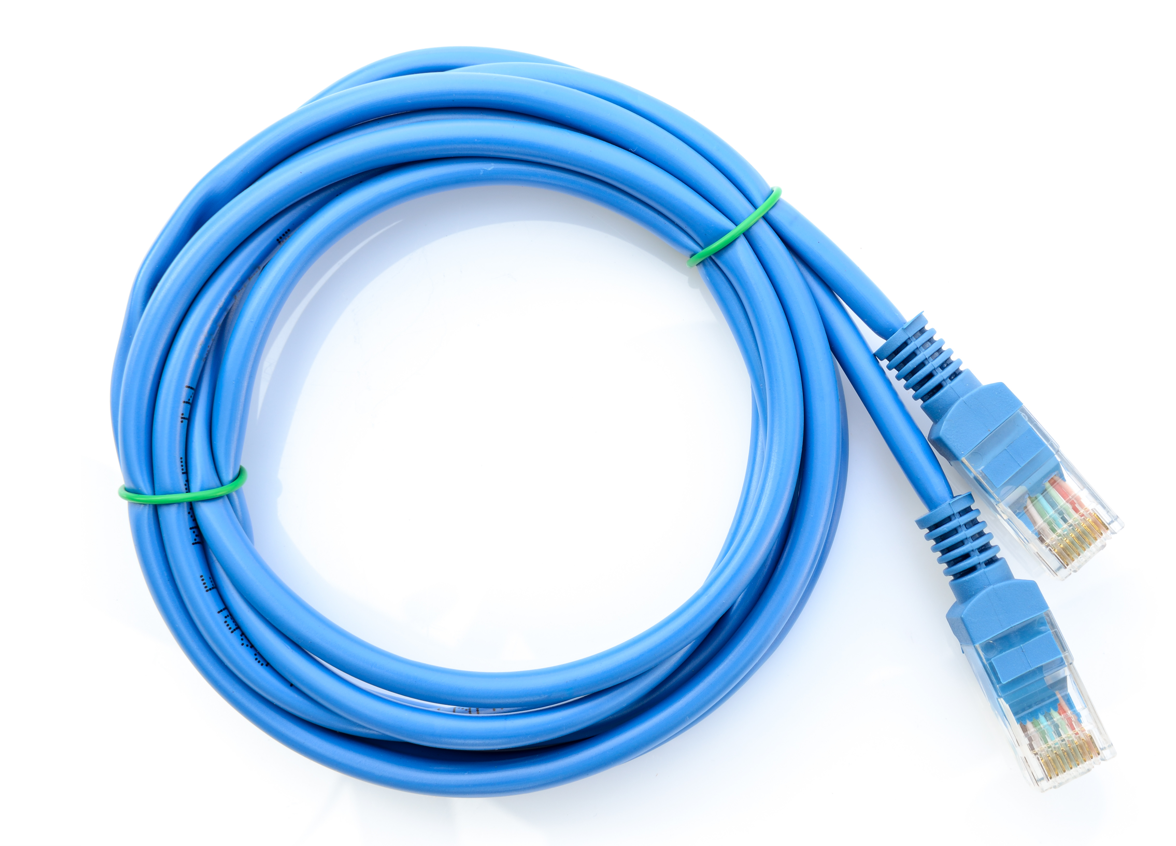

| 材質 |
|
|---|---|
| メリット |
|
| デメリット |
|
FC接続(8Gb/16Gb/32Gbなど)やギガビットイーサネット(GbE)接続などで利用される。
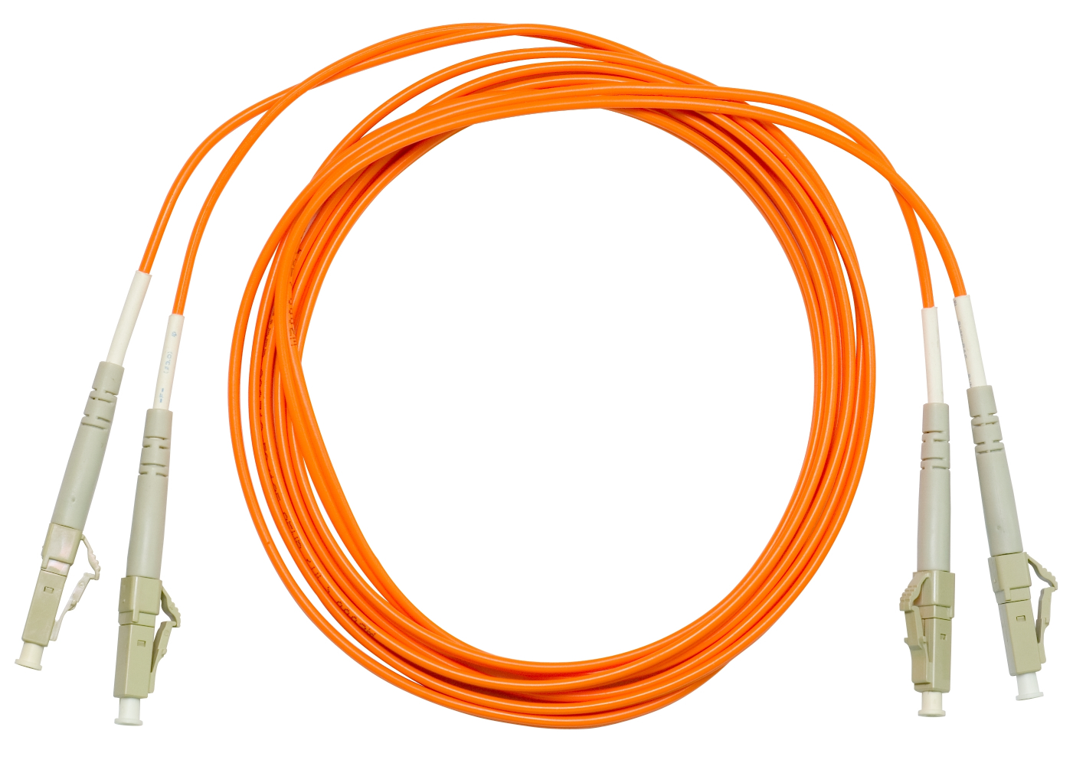
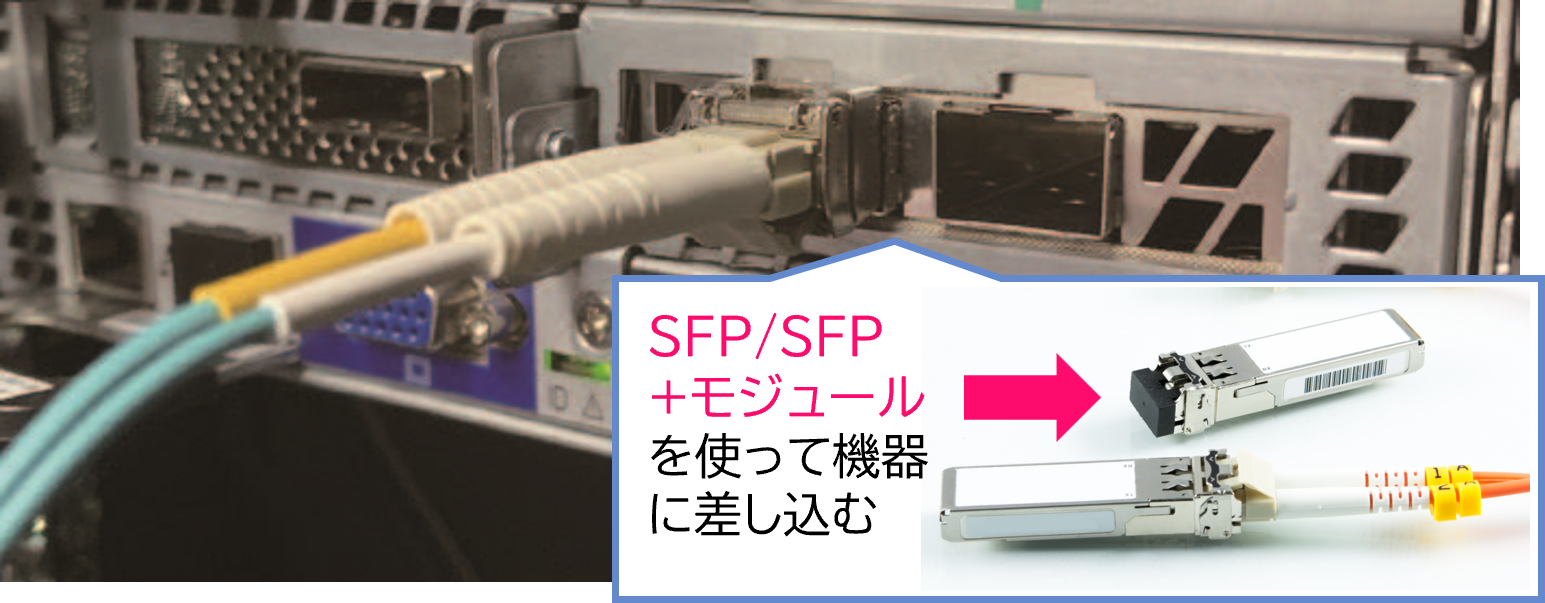
| 材質 |
|
|---|---|
| メリット |
|
| デメリット |
|
両端にSFP+などのモジュールが接続されている。ギガビットイーサネット(GbE)接続で利用される。


| 材質 |
|
|---|---|
| メリット |
|
| デメリット |
|


今回はストレージ業界でよく使われる通信プロトコルと接続ケーブル、インターフェースを解説しました。
次回はデータの通信速度とストレージの性能指標I/O・IOPS・レイテンシについて解説します。